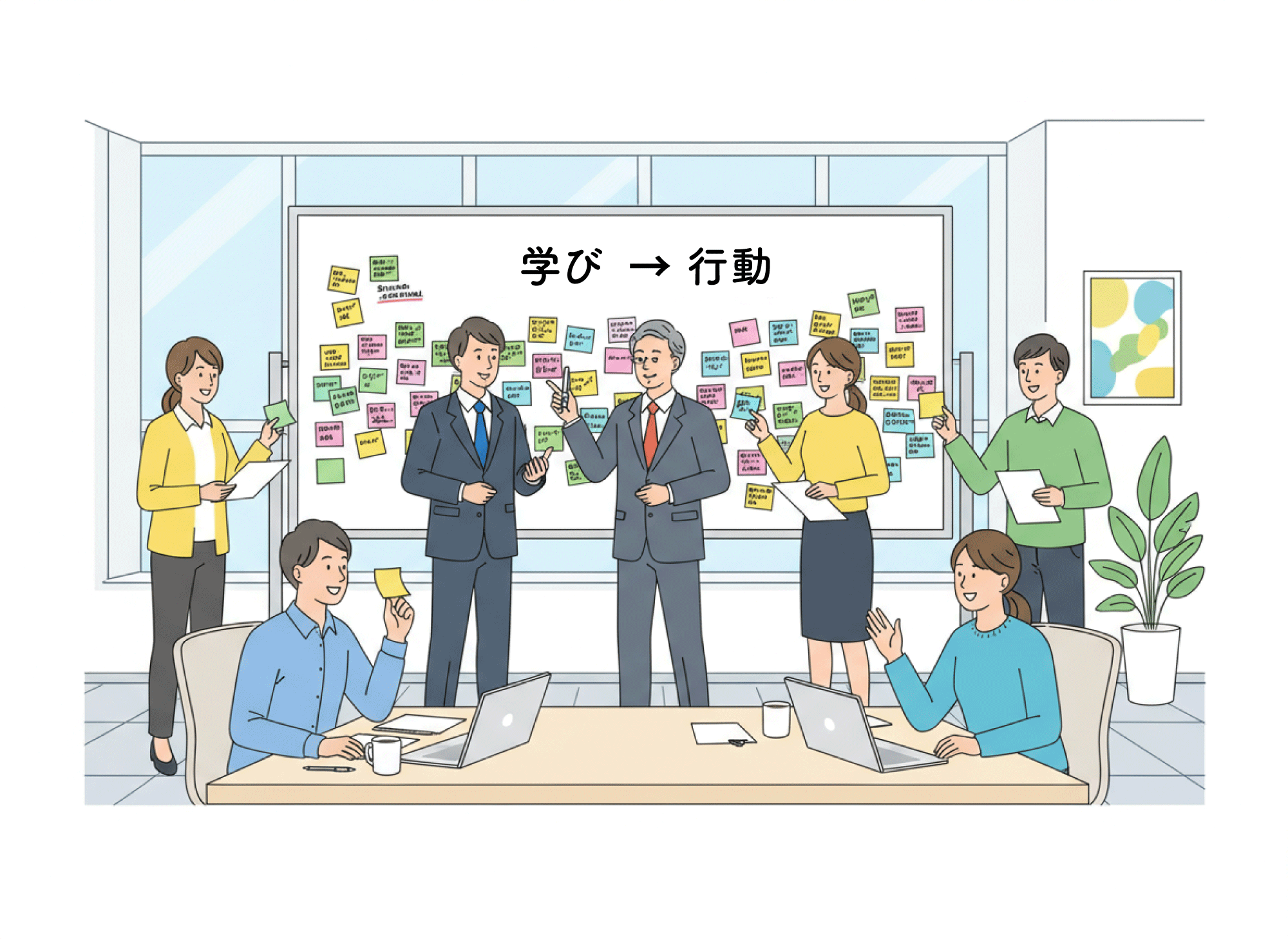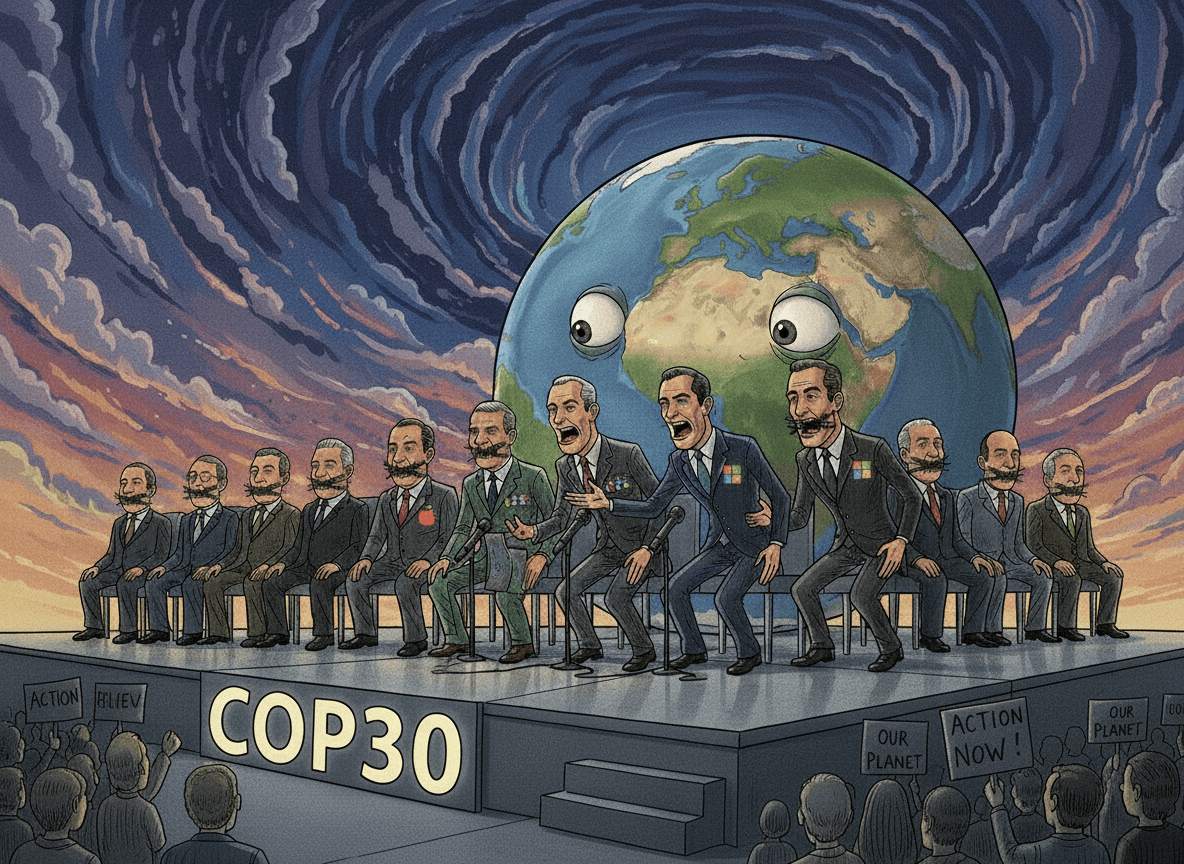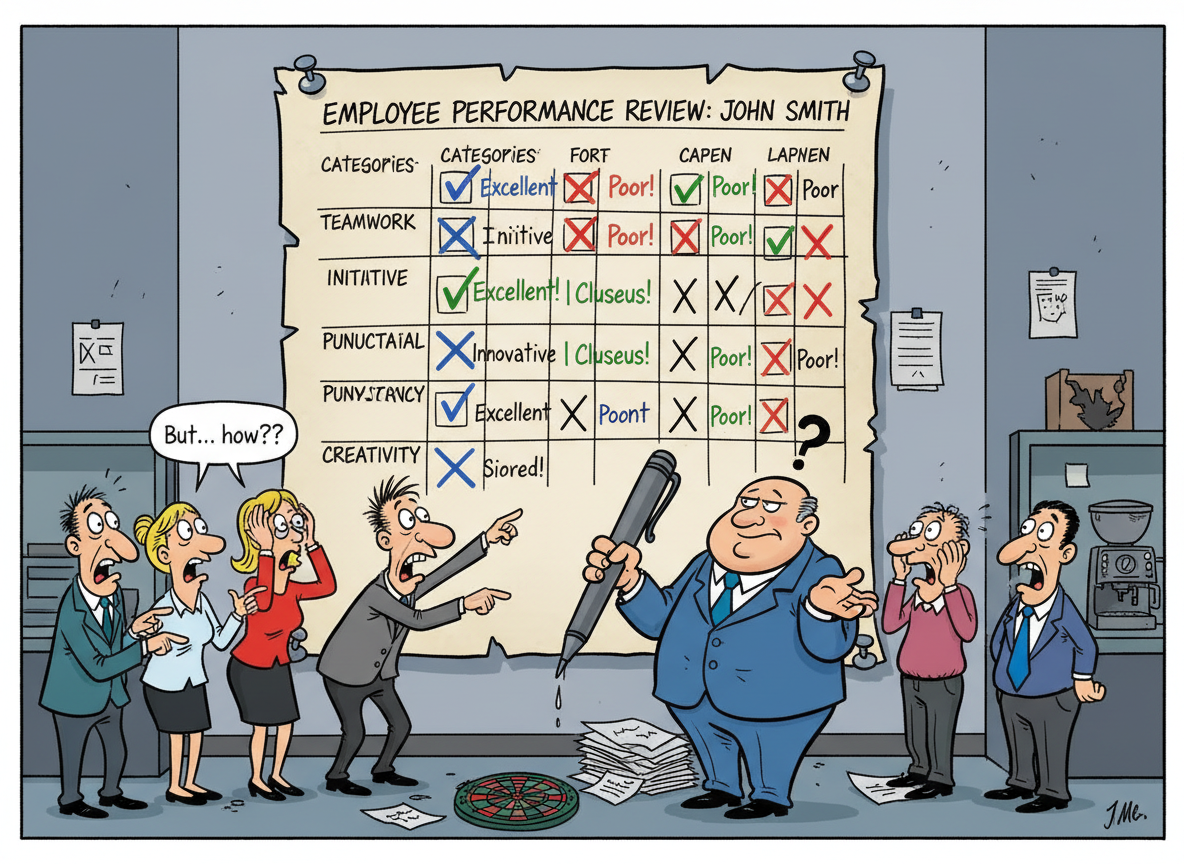指示があるのに動けない
会議では発言も多く、社内でも指示を出す。しかしその指示は具体性に欠け、受け取った部下はどう動けばよいのか迷ってしまう──そんな管理職が少なくない。言葉や指示は飛ぶものの、自らの手で形に残る成果は示されず、現場は停滞する。
確かに怠慢に見えることもあるが、必ずしもそうではない。克服しようと努力している人も少なくないが、「学んだことをどう行動に変えればよいのか」が分からず、成果を形にできないまま立ち止まっているのが実情だ。こういう場面では、研修や教育を繰り返しても改善は難しい。このような状況下では、学びを必ず“行動”に変える仕組みを制度として組織構造に埋め込むことが、現実的で効果的な解決策になる。
昭和〜平成の組織文化が生んだ「学び止まりの管理職」
管理職が学びを行動に変えられない背景には、日本の昭和〜平成期の組織文化がある。
当時の企業社会では、上位者の意向に沿わない提案や従来の枠組みから外れる提案は歓迎されにくい傾向があった。組織においては「和を乱さない」ことが重視され、成果物よりも調整や根回しが評価される。会議に参加し、空気を読むことが管理職の役割とされ、学びを行動に変えることは必須ではなかった。
その結果、管理職は「学びを行動に変えないまま昇進する」構造に置かれてきた。本人もまた、責任を負うことを避け、抽象的な言葉に逃げることで、結果的に具体的な行動を遠ざけてきた。結果として、学びを実務に結びつける訓練が不足したまま管理職になった層が生まれた。
こうした文化的背景の中で育った管理職は、現場で学びを行動に変えることを避けがちになる。その結果、日常の業務では曖昧な指示や責任の不在といった“停滞の場面”が繰り返される。次の章では、その典型的な場面と、それを制度でどう解消するかを見ていきたい。
よくある停滞の場面と制度での解決
現場で繰り返される停滞には、いくつかの典型的なパターンがある。
ひとつは、会議で「まず検討しておいて」と曖昧な指示だけが飛ぶ場面だ。部下は何をどう進めればよいのか分からず、結局時間だけが過ぎてしまう。こういう状況では、指示のたびに目的や期待成果、期限を一枚のシートに記録し、責任者を明示する制度を組み込むことで、曖昧さを防ぐことができる。
もうひとつは、会議そのものは活発でも、終わった後に「誰が何をいつまでにやるのか」が決まらず、次回までに進捗がない場面だ。これを防ぐには、会議終了時に必ずアクションログを残し、次回の冒頭で進捗確認を制度化することが有効だ。宿題が消えることなく、会議が次の行動につながるようになる。
さらに、新しい提案が出ても「前例がない」「リスクがある」として消えてしまう場面もある。提案が空気に吸われてしまうのだ。ここでは、短期間・低予算で試せる小さな実験枠を制度として設け、結果が成功でなくても「試した事実」と「学び」を評価対象に含めることが重要になる。挑戦が形になり、失敗も価値として残る仕組みがあれば、提案は消えずに次の行動へとつながる。
人事考課に組み込む──学びを行動に変える評価制度
教育で「学びの重要性」を説くよりも、評価制度に「学びを行動に変えたかどうか」を組み込む方が効果的だ。具体的には、人事評価表と360度評価に以下のような運用を加える。
- 人事評価表の記入例
評価表に「学びを行動に変えた事例」を記入する欄を設ける。- 例:研修で学んだ知識を使い、会議資料のフォーマットを改善した
- 例:自己啓発で得た知見を活かし、業務フローを簡略化した
→ 記入は「行動内容」「成果」「影響」の3行で十分。
- 360度評価の質問例
評価者(上司・同僚・部下)に次の質問を投げる:- この人の学びは、あなたの業務に役立ちましたか?
- この人の提案は、具体的で実行可能でしたか?
- この人の行動は、次のステップにつながりましたか?
- 運用フロー
- 四半期ごとに人事が件数と事例を集計
- 360度評価で「役立ち度・具体性・実行性」を確認
- 昇進・昇給の判断材料に反映
“学びを行動に変える仕組み”を組み込む
昭和〜平成の日本的組織文化は、異端を避ける構造によって「学びを行動に変える」機会を奪ってきた。世界的にも保守的な傾向はあるが、日本では特に強く制度化されていた。このような状況下では、教育で学び直すのではなく、人事考課や組織構造に“学びを行動に変える仕組み”を組み込むことが現実的な解決策である。
問われているのは、知識を増やすことではなく、学びを行動に変える勇気である。